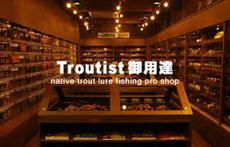2017年01月20日
渓流ルアーロッド2017 Ver.

まずはロッドの基本設計
今回は思想とターゲットが明確なのでロッドの仕様自体の迷いは少なかったが、
初のブランクから完全創作なので、どんなロッドになっても自己責任。
それを「使ってみたい」と言ってくれたMTの為にも、今の僕に出来る精一杯のものにしたい。
アマチュアの特権である、工数と原価に縛られる事無く究極を突き詰める。
通常、カーボンブランクは各種プリプレグをマンドレルに巻いて作られるが、今回のブランクは、プリプレグからの選択による安易な?カーボンではなく、プリプレグ以前のカーボンとマトリックス樹脂を別々に使用しての拘り品。
そのカーボンのプロとの打合せで知り得た実態は驚愕モノで、
カーボンだけでも引張強度・引張弾性率・織物か繊維か不織布等で30種を超え、組み合わせる樹脂も10種類を超え、この時点で組み合わせは400通りを超え、
更に製造過程のノウハウは、密度・方向・テンション・ナノなんちゃら・部位別の樹脂の含有率・高弾性を外側?内側?サンドイッチ?それを1本のブランクの中に複合的に使用。
圧力だけでも、どの部位にどれだけの圧力をどういう時系列でかけるか?温度も然り。
まさに天文学的ノウハウであり、素人が口を出しても恥をかくだけなので詳細はプロにお任せで。
僕が言えるのは、弾性率40トンを超える数種のカーボンの組み合わせによるという事だけ。
※ちょっと凄ーく疑問点、東レを以ってしてもカーボンの比率は80%が最高なのに、釣り竿で表記の「カーボン率99%」の根拠ってなに?
出来上がってきたブランクをすぐにでも曲げて見たいので、目論んだ部分で切断、フェルールを作り、スレッドを巻く。
切断部の断面を見るとパイプの肉厚は恐ろしい程に肉薄だ。
ブランクは単体では10グラム以下。
こうして作られたブランクを触ると、市販ロッド越える高弾性・低レジンなのに、脆い感触が全く無い。
某STSより高弾性なのに(折れそうな)恐怖を感じないのだ。
「凄い!」ファクトリー品質を垣間見ることが出来た。
リールシートは装飾や高級感ではウッドやメタルにて優れた物は多々あるが、
基本性能の観点から選ぶと僕の中ではトータルでDPSを超える物が思い浮かばない。
DPS‐16を大量購入し、ブリッジ形状に切り欠いたり、肉抜きをしたり、色々と試す。
そして、キッチンを占拠して、パイプやフードのカーボン化を試みる。
フェルール製作みたいに簡単では無かったが、数回の失敗作の後にようやく1個できた。
ここで「壁」に 大!激!突!。
アレコレのパーツをカーボンに置換したが、フジDPSより鈍感になってないかい?。
ブランクに仮組みしグリップに(ウクレレ用の)クリップチューナーを付けて見ても明らかに鈍感になっているのだ!
原点に立ち返りカーボンについての勉強をすると、驚愕の事実が!。
まず重量であるが、フジ標準材質である高強度ナイロンの比重1.1に対し、
カーボン自体は比重1.6もあり全然軽くない!。
そして
カーボンが制振材として振動減衰特性に優れ、振動が瞬時に減衰すると記述されてるのです。
(スピーカーの防振ベースに使われるくらいだから、当然か。)
釣り竿メーカーの謳う、カーボンの「軽量・高感度」の根拠って何なんだ?。
あっちゃ~ぁ・・・手間と大金を掛けて、せっせと鈍感にしていたのである。
まぁ、勉強になったと思えばいいか。
結局今回はDPSをそのまま使用する事に。
(今までの苦労は何だったんだ!?)
アップロックで一通り組んでMTに振らせるも、小指部にネジが当るのが好みじゃないらしい。
しかしダウンロックで親指部分にスクリューが来るのは僕の好みじゃない。
熱をかけずにブランクを無傷で外そうとすれば、リールシートを破壊するしか方法が思い付かないのが痛いところ。
またもやDPS‐16を買いなおし。(途中でボツ案になった試作も含めると何本目やら)
同時に、KDPS‐16Sと、マタギのAC‐KD17a(コルク)を購入。
ちまちましたショートパーツの積み重ねでもアッと言う間に1万円を超える(; ;)
ブランクとリールシートを結合させるアーバーにも妥協無き拘りを。

リアフード部はコンフォート性を求めてコルクアーバー。
まぁ、これは普通。
フロントアーバーは、情報(振動)伝達性を求めて十字型のアルミナに、異物進入を防ぐ蓋として0.2tのドライカーボン。

アルミナの製作方法を、真似する人は居ないと思うけど、一応参考までに記しておきます。
僕自身がいわゆるビトリファイド製法を参考に試行錯誤して辿り着いた方法なので、参考にされる皆さんも自己責任でお願いします。
道具類は、溶接用手袋(ホームセンターで数百円)・レンガ・漆喰(しっくい)セメント・BBQ用ガスバーナー。
材料はアルミナとガラスの微粉末です。が、
実はアルミナもガラス(ビトリファイド)も少量過ぎて売ってません。
インターネットで砥石工場などを検索して、工場内にこぼれている物を貰ってきます(タダ)。
レンガの上に砂と漆喰セメントで簡易な受け型を作り、アルミナとガラスが混ざった粉末を詰めて準備完了。
BBQ用のガスバーナーでひたすらゴーゴーとオレンジ色を持続させて熱します。
ここで本当に真剣な注意事項を。
輻射熱だけでも火傷しますので、絶対に手や顔などを近付けないで!
水をかけると瞬間で猛烈に飛び散りますので、絶対に水をかけないで!
赤熱⇒灰白くなっても、ゆうに数百度はあるので一晩は冷ました方が安心です。
最も重要なのは、絶対に誰も近付かない環境を確保して下さい!
とにかく重大な危険が伴う温度なのでくれぐれも安易に真似しないように。
一晩冷ました物は、投入した素材に対して何故だか大きくなったり縮小したりしちゃっているので、幾つも作っていればいずれマトモな1個ができるでしょう。
凡その物ができたら、あとは旧石器(打製石器)を作る要領で超硬の棒やタングステン棒でコツコツ。
オイルストーンやダイヤモンド砥粒でシコシコ仕上げます。
ガイドはトルザイト(改)にする事に。
ガイドフットの裏を取付け位置ブランク外径のRに合わせて擦り合わせ。
ガイドは、モーメントで考えると0.1gが大きく影響してくると思い軽量化。

トップガイドも過剰な強度を適正化する。

しかーし!自作ブランクゆえにガイドセッティングの参考も無く、悶絶の繰り返し。
ガイドをスレッドで仮止め⇒振ってはバラシ⇒仮止め⇒振ってはバラシ⇒を繰り返すが、僕の気持ちにスーッと入ってくるセッティングにならない。
ベリーが仕事をするように意識して創ったブランクなのだが、ちょっとベリーが曲がり過ぎるのだ。
思い切ってブランクの再カットに着手。
またもやフェルール製作からやり直し。
この時に切断したベリーの切れ端が、摘まんだだけで「パシャ」と潰れてしまってビックリ!
ブランク単体では円(パイプ)形状を辛うじて保つのがやっとなくらいギリギリ薄肉のセッティングなのだ。
ベリーを短くしてフェルールを作り直した試作は、
こんどは思わずニヤケルくらいにキマッタ!!
これぞ「リアルハンド」と言えるセッティングだぜぃ!(^^)V
本番のガイドスレッドも直径0.1ミリ以下の超高分子量ポリエチレン UHMWの撚り糸を使い、
前回の3Pロッドで試験済みである、フッ素樹脂と硬化樹脂の混合コーティングを必要最低限だけ含浸。
スレッド巻き後にコッテリ塗るのではなく、あくまでスレッドに含浸させるだけ。
表面の保護は含浸から染み出たフッ素樹脂(テフロン)の膜が担う。
これとて、ガイドフットとブランクが密着し、樹脂で隙間を埋める必要が無いから可能な手法となるのだが。
ダイワAGSより遥かに軽いゼ!V(^Q^)V
この時点ではまだガイドとリールシートを装着しただけの状態で、コルクやEVAのグリップ材は未装着。
MTがヴァンキッシュを使用するのを考慮し、RARENIUM CI4+C2000HGSを装着してテストを進めてきた。
なんてこったい!リヤグリップを付ける前に(当初の狙い重心位置である)リールフット前2センチでバランス取れちゃってるではないか!
このままリヤグリップのコルクを装着すると、リヤヘビーになってしまうのは想像に難しくない。
強度と握り心地のギリギリまでリヤグリップを削り込む。
僕ら素人は穴埋めにはジャストエースのCORK SEALSを使用する事が多いのですが、
こいつがちょっとクセモノで、色が白っぽくコルクに似つかわしくないし、固まった後の硬さがコルクっぽくない!。
なので、実際のグリップを削ったコルク粉末を投入してマゼマゼ。
これで違和感は薄らいだかな。
やったーー!!!できたーー!!!\(^o^)/
リヤグリップまで装着した一応の完成形で重心は、リールフットの付け根ギリ!
結局リールシートの軽量化は一切ナシで総重量34.7グラム。

RARENIUMとの組み合わせでも200グラムを切った。
セパレートグリップやスケルトンシートでは無い、フルグリップのロッドとしては最軽量の部類に入るのではないでしょうか?
さてと!MT用の本番ロッドに取り掛からなきゃ(焦)
ロッドスペック
●サイズ:5フィート3インチ
●継数:2pcs
●自重:34.7g
●ルアー:キャストで気持ち良いのは1g~4g
●ノット:コブができない摩擦系ノット指定。
そのカーボンのプロとの打合せで知り得た実態は驚愕モノで、
カーボンだけでも引張強度・引張弾性率・織物か繊維か不織布等で30種を超え、組み合わせる樹脂も10種類を超え、この時点で組み合わせは400通りを超え、
更に製造過程のノウハウは、密度・方向・テンション・ナノなんちゃら・部位別の樹脂の含有率・高弾性を外側?内側?サンドイッチ?それを1本のブランクの中に複合的に使用。
圧力だけでも、どの部位にどれだけの圧力をどういう時系列でかけるか?温度も然り。
まさに天文学的ノウハウであり、素人が口を出しても恥をかくだけなので詳細はプロにお任せで。
僕が言えるのは、弾性率40トンを超える数種のカーボンの組み合わせによるという事だけ。
※ちょっと凄ーく疑問点、東レを以ってしてもカーボンの比率は80%が最高なのに、釣り竿で表記の「カーボン率99%」の根拠ってなに?
出来上がってきたブランクをすぐにでも曲げて見たいので、目論んだ部分で切断、フェルールを作り、スレッドを巻く。
切断部の断面を見るとパイプの肉厚は恐ろしい程に肉薄だ。
ブランクは単体では10グラム以下。
こうして作られたブランクを触ると、市販ロッド越える高弾性・低レジンなのに、脆い感触が全く無い。
某STSより高弾性なのに(折れそうな)恐怖を感じないのだ。
「凄い!」ファクトリー品質を垣間見ることが出来た。
リールシートは装飾や高級感ではウッドやメタルにて優れた物は多々あるが、
基本性能の観点から選ぶと僕の中ではトータルでDPSを超える物が思い浮かばない。
DPS‐16を大量購入し、ブリッジ形状に切り欠いたり、肉抜きをしたり、色々と試す。
そして、キッチンを占拠して、パイプやフードのカーボン化を試みる。
フェルール製作みたいに簡単では無かったが、数回の失敗作の後にようやく1個できた。
ここで「壁」に 大!激!突!。
アレコレのパーツをカーボンに置換したが、フジDPSより鈍感になってないかい?。
ブランクに仮組みしグリップに(ウクレレ用の)クリップチューナーを付けて見ても明らかに鈍感になっているのだ!
原点に立ち返りカーボンについての勉強をすると、驚愕の事実が!。
まず重量であるが、フジ標準材質である高強度ナイロンの比重1.1に対し、
カーボン自体は比重1.6もあり全然軽くない!。
そして
カーボンが制振材として振動減衰特性に優れ、振動が瞬時に減衰すると記述されてるのです。
(スピーカーの防振ベースに使われるくらいだから、当然か。)
釣り竿メーカーの謳う、カーボンの「軽量・高感度」の根拠って何なんだ?。
あっちゃ~ぁ・・・手間と大金を掛けて、せっせと鈍感にしていたのである。
まぁ、勉強になったと思えばいいか。
結局今回はDPSをそのまま使用する事に。
(今までの苦労は何だったんだ!?)
アップロックで一通り組んでMTに振らせるも、小指部にネジが当るのが好みじゃないらしい。
しかしダウンロックで親指部分にスクリューが来るのは僕の好みじゃない。
熱をかけずにブランクを無傷で外そうとすれば、リールシートを破壊するしか方法が思い付かないのが痛いところ。
またもやDPS‐16を買いなおし。(途中でボツ案になった試作も含めると何本目やら)
同時に、KDPS‐16Sと、マタギのAC‐KD17a(コルク)を購入。
ちまちましたショートパーツの積み重ねでもアッと言う間に1万円を超える(; ;)
ブランクとリールシートを結合させるアーバーにも妥協無き拘りを。

リアフード部はコンフォート性を求めてコルクアーバー。
まぁ、これは普通。
フロントアーバーは、情報(振動)伝達性を求めて十字型のアルミナに、異物進入を防ぐ蓋として0.2tのドライカーボン。

アルミナの製作方法を、真似する人は居ないと思うけど、一応参考までに記しておきます。
僕自身がいわゆるビトリファイド製法を参考に試行錯誤して辿り着いた方法なので、参考にされる皆さんも自己責任でお願いします。
道具類は、溶接用手袋(ホームセンターで数百円)・レンガ・漆喰(しっくい)セメント・BBQ用ガスバーナー。
材料はアルミナとガラスの微粉末です。が、
実はアルミナもガラス(ビトリファイド)も少量過ぎて売ってません。
インターネットで砥石工場などを検索して、工場内にこぼれている物を貰ってきます(タダ)。
レンガの上に砂と漆喰セメントで簡易な受け型を作り、アルミナとガラスが混ざった粉末を詰めて準備完了。
BBQ用のガスバーナーでひたすらゴーゴーとオレンジ色を持続させて熱します。
ここで本当に真剣な注意事項を。
輻射熱だけでも火傷しますので、絶対に手や顔などを近付けないで!
水をかけると瞬間で猛烈に飛び散りますので、絶対に水をかけないで!
赤熱⇒灰白くなっても、ゆうに数百度はあるので一晩は冷ました方が安心です。
最も重要なのは、絶対に誰も近付かない環境を確保して下さい!
とにかく重大な危険が伴う温度なのでくれぐれも安易に真似しないように。
一晩冷ました物は、投入した素材に対して何故だか大きくなったり縮小したりしちゃっているので、幾つも作っていればいずれマトモな1個ができるでしょう。
凡その物ができたら、あとは旧石器(打製石器)を作る要領で超硬の棒やタングステン棒でコツコツ。
オイルストーンやダイヤモンド砥粒でシコシコ仕上げます。
ガイドはトルザイト(改)にする事に。
ガイドフットの裏を取付け位置ブランク外径のRに合わせて擦り合わせ。
ガイドは、モーメントで考えると0.1gが大きく影響してくると思い軽量化。

トップガイドも過剰な強度を適正化する。

しかーし!自作ブランクゆえにガイドセッティングの参考も無く、悶絶の繰り返し。
ガイドをスレッドで仮止め⇒振ってはバラシ⇒仮止め⇒振ってはバラシ⇒を繰り返すが、僕の気持ちにスーッと入ってくるセッティングにならない。
ベリーが仕事をするように意識して創ったブランクなのだが、ちょっとベリーが曲がり過ぎるのだ。
思い切ってブランクの再カットに着手。
またもやフェルール製作からやり直し。
この時に切断したベリーの切れ端が、摘まんだだけで「パシャ」と潰れてしまってビックリ!
ブランク単体では円(パイプ)形状を辛うじて保つのがやっとなくらいギリギリ薄肉のセッティングなのだ。
ベリーを短くしてフェルールを作り直した試作は、
こんどは思わずニヤケルくらいにキマッタ!!
これぞ「リアルハンド」と言えるセッティングだぜぃ!(^^)V
本番のガイドスレッドも直径0.1ミリ以下の超高分子量ポリエチレン UHMWの撚り糸を使い、
前回の3Pロッドで試験済みである、フッ素樹脂と硬化樹脂の混合コーティングを必要最低限だけ含浸。
スレッド巻き後にコッテリ塗るのではなく、あくまでスレッドに含浸させるだけ。
表面の保護は含浸から染み出たフッ素樹脂(テフロン)の膜が担う。
これとて、ガイドフットとブランクが密着し、樹脂で隙間を埋める必要が無いから可能な手法となるのだが。
ダイワAGSより遥かに軽いゼ!V(^Q^)V
この時点ではまだガイドとリールシートを装着しただけの状態で、コルクやEVAのグリップ材は未装着。
MTがヴァンキッシュを使用するのを考慮し、RARENIUM CI4+C2000HGSを装着してテストを進めてきた。
なんてこったい!リヤグリップを付ける前に(当初の狙い重心位置である)リールフット前2センチでバランス取れちゃってるではないか!
このままリヤグリップのコルクを装着すると、リヤヘビーになってしまうのは想像に難しくない。
強度と握り心地のギリギリまでリヤグリップを削り込む。
僕ら素人は穴埋めにはジャストエースのCORK SEALSを使用する事が多いのですが、
こいつがちょっとクセモノで、色が白っぽくコルクに似つかわしくないし、固まった後の硬さがコルクっぽくない!。
なので、実際のグリップを削ったコルク粉末を投入してマゼマゼ。
これで違和感は薄らいだかな。
やったーー!!!できたーー!!!\(^o^)/
リヤグリップまで装着した一応の完成形で重心は、リールフットの付け根ギリ!
結局リールシートの軽量化は一切ナシで総重量34.7グラム。

RARENIUMとの組み合わせでも200グラムを切った。
セパレートグリップやスケルトンシートでは無い、フルグリップのロッドとしては最軽量の部類に入るのではないでしょうか?
さてと!MT用の本番ロッドに取り掛からなきゃ(焦)
ロッドスペック
●サイズ:5フィート3インチ
●継数:2pcs
●自重:34.7g
●ルアー:キャストで気持ち良いのは1g~4g
●ノット:コブができない摩擦系ノット指定。
Posted by さかニイ at 14:36│Comments(4)
│釣り道具
この記事へのコメント
変態過ぎ〜〜(*´艸`)キャ
Posted by こも at 2017年01月20日 15:04
こもさん
だって、市販品ではつまんないんだもーん!(笑)
だって、市販品ではつまんないんだもーん!(笑)
Posted by さかニイ at 2017年01月20日 18:37
at 2017年01月20日 18:37
 at 2017年01月20日 18:37
at 2017年01月20日 18:37はじめまして。
ボクは主に海のアジングロッドを制作しています。
対象魚種は違えど、同じくロッドビルドを趣味とする者から見ても・・・
相当変態ですね(笑)
プライベートビルダー最大の壁である「オリジナルブランク」を手にするなんて羨ましい限りです。
ボクは主に海のアジングロッドを制作しています。
対象魚種は違えど、同じくロッドビルドを趣味とする者から見ても・・・
相当変態ですね(笑)
プライベートビルダー最大の壁である「オリジナルブランク」を手にするなんて羨ましい限りです。
Posted by tobbiny&co. at 2017年02月04日 18:50
at 2017年02月04日 18:50
 at 2017年02月04日 18:50
at 2017年02月04日 18:50>tobbiny&coさん
コメント有難う御座います。
ロッドビルドも数を重ねるとドンドン変態になっていきますね。
最軽量ロッドも凄いと思います。
コメント有難う御座います。
ロッドビルドも数を重ねるとドンドン変態になっていきますね。
最軽量ロッドも凄いと思います。
Posted by さかニイ at 2017年02月07日 13:20
at 2017年02月07日 13:20
 at 2017年02月07日 13:20
at 2017年02月07日 13:20