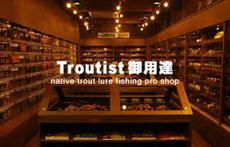2016年11月24日
ルアーに仕込むタングステンウェイトの拘り。
今年は諸般の事情で釣りに行く機会が激減している。
そんな昨今は暇を持て余し、道具いじりに拘ってしまうのが釣り人の性。
今日はルアーを自作する時のウェイトの話など。
そもそもルアー作りを始めた頃は安価なガン玉を使ってました。
レイチューンのストリームアーマーがプラ化され(アゴの消耗を気にせず)ガンガン使い出すと、ダート系のアクションを多用するようになり。
おのずとダートに特化したルアーを欲するようになるが、市場を見渡しても見当たらない。
無いならば作ってみようと試作を繰り返すと、重心の一点集中化が非常に重要な事が分かってきた。
時を同じくして下記の現象も発生したのだ。
そんな昨今は暇を持て余し、道具いじりに拘ってしまうのが釣り人の性。
今日はルアーを自作する時のウェイトの話など。
そもそもルアー作りを始めた頃は安価なガン玉を使ってました。
レイチューンのストリームアーマーがプラ化され(アゴの消耗を気にせず)ガンガン使い出すと、ダート系のアクションを多用するようになり。
おのずとダートに特化したルアーを欲するようになるが、市場を見渡しても見当たらない。
無いならば作ってみようと試作を繰り返すと、重心の一点集中化が非常に重要な事が分かってきた。
時を同じくして下記の現象も発生したのだ。
僕はフックをシングルに換える事が多く、ルアーのアクション性能が顕著(過敏)に出てしまう傾向がある。
タングステンウェイト搭載を名乗るルアーのアクションのバラつきが大きく、胴体のヒビ割れを機にウェイトが気になって取り出して見た。
直径7ミリの球が3粒入っており、其々を量ると、3.3g・3.0g・2.5g。
もう1本、橋脚に激突させて戦線離脱していた方は3.2g・3.1g・3.2gと驚くほど重さが違う!
ルアーメーカーにタングステンウェイトを卸しているウェイト屋さんは、自社検査を実施と謳っているので、2.5g(比重14)は許容範囲ということか?
まぁ自社検査っても、現実的には「割れ」「欠け」の目視検査程度で、比重を1個1個量るのは不可能というもの。
このウェイト差は粉末材料の撹拌工程が不十分なまま球状に固めてしまう事が原因かと想像できる。
ということは、1粒あたりでも重量の偏りがあるのではないか?
ウェイト屋さんが真球度の自社検査をしてると信用して、精密石定盤の上に置いてみた。
やはりと言うべきか、停止位置の偏りが見られる。(毎回同じ向きで止まる)
バルサルアーで「バルサの比重の差で動きが云々」と聞くが、確かに浮力の傾きに関してはバルサの偏りであろう、
しかし、重心の傾きに関してはウェイトの内部の重心の偏りによる影響の方が大きい気がする。
僕自身のルアーはTIG(アルゴン)溶接のハンドピースの溶接棒の残材を流用するようになっていた。
素材が充分に撹拌され製作される棒状を切断した「円柱」の方が比重の偏りが無いであろうと思うのと、
溶接棒は融点3400℃以上というタングステンの耐熱性を求めた使途なので、間違いなく純度の高さが保証されているから。
溶接屋さんとのコネクションが希薄になったのでTIG溶接棒の新品を買いますが、それでも遥かに信頼できる素材が釣り系のタングステンウェイトより安価で入手できます。
切断は百均のダイヤモンドヤスリでV溝を入れてハンマーでパキンッと折ってます。
今まで自作ルアーのウェイトは①鉛ウェイト(ガン玉)、②市販のタングステンウェイト、そして③純タングステン(TIG溶接棒)と推移してきましたが、
①→②の変化よりも、②→③の時の方が「球」→「円柱」の形状の変化もあり劇的な性能アップが実感できたので、それ以来タングステン円柱ばかりです。
実際には純度の高いタングステンウェイトも売っており、渓流ルアー1個あたり数百円のコストアップで劇的な性能アップが得られるのでアリではないでしょうか。
高品質&安価なタングステンウェイトのお話しでした。
タングステンウェイト搭載を名乗るルアーのアクションのバラつきが大きく、胴体のヒビ割れを機にウェイトが気になって取り出して見た。
直径7ミリの球が3粒入っており、其々を量ると、3.3g・3.0g・2.5g。
もう1本、橋脚に激突させて戦線離脱していた方は3.2g・3.1g・3.2gと驚くほど重さが違う!
ルアーメーカーにタングステンウェイトを卸しているウェイト屋さんは、自社検査を実施と謳っているので、2.5g(比重14)は許容範囲ということか?
まぁ自社検査っても、現実的には「割れ」「欠け」の目視検査程度で、比重を1個1個量るのは不可能というもの。
このウェイト差は粉末材料の撹拌工程が不十分なまま球状に固めてしまう事が原因かと想像できる。
ということは、1粒あたりでも重量の偏りがあるのではないか?
ウェイト屋さんが真球度の自社検査をしてると信用して、精密石定盤の上に置いてみた。
やはりと言うべきか、停止位置の偏りが見られる。(毎回同じ向きで止まる)
バルサルアーで「バルサの比重の差で動きが云々」と聞くが、確かに浮力の傾きに関してはバルサの偏りであろう、
しかし、重心の傾きに関してはウェイトの内部の重心の偏りによる影響の方が大きい気がする。
僕自身のルアーはTIG(アルゴン)溶接のハンドピースの溶接棒の残材を流用するようになっていた。
素材が充分に撹拌され製作される棒状を切断した「円柱」の方が比重の偏りが無いであろうと思うのと、
溶接棒は融点3400℃以上というタングステンの耐熱性を求めた使途なので、間違いなく純度の高さが保証されているから。
溶接屋さんとのコネクションが希薄になったのでTIG溶接棒の新品を買いますが、それでも遥かに信頼できる素材が釣り系のタングステンウェイトより安価で入手できます。
切断は百均のダイヤモンドヤスリでV溝を入れてハンマーでパキンッと折ってます。
今まで自作ルアーのウェイトは①鉛ウェイト(ガン玉)、②市販のタングステンウェイト、そして③純タングステン(TIG溶接棒)と推移してきましたが、
①→②の変化よりも、②→③の時の方が「球」→「円柱」の形状の変化もあり劇的な性能アップが実感できたので、それ以来タングステン円柱ばかりです。
実際には純度の高いタングステンウェイトも売っており、渓流ルアー1個あたり数百円のコストアップで劇的な性能アップが得られるのでアリではないでしょうか。
高品質&安価なタングステンウェイトのお話しでした。
Posted by さかニイ at 15:22│Comments(0)
│釣り道具